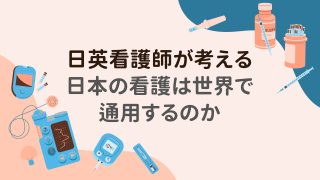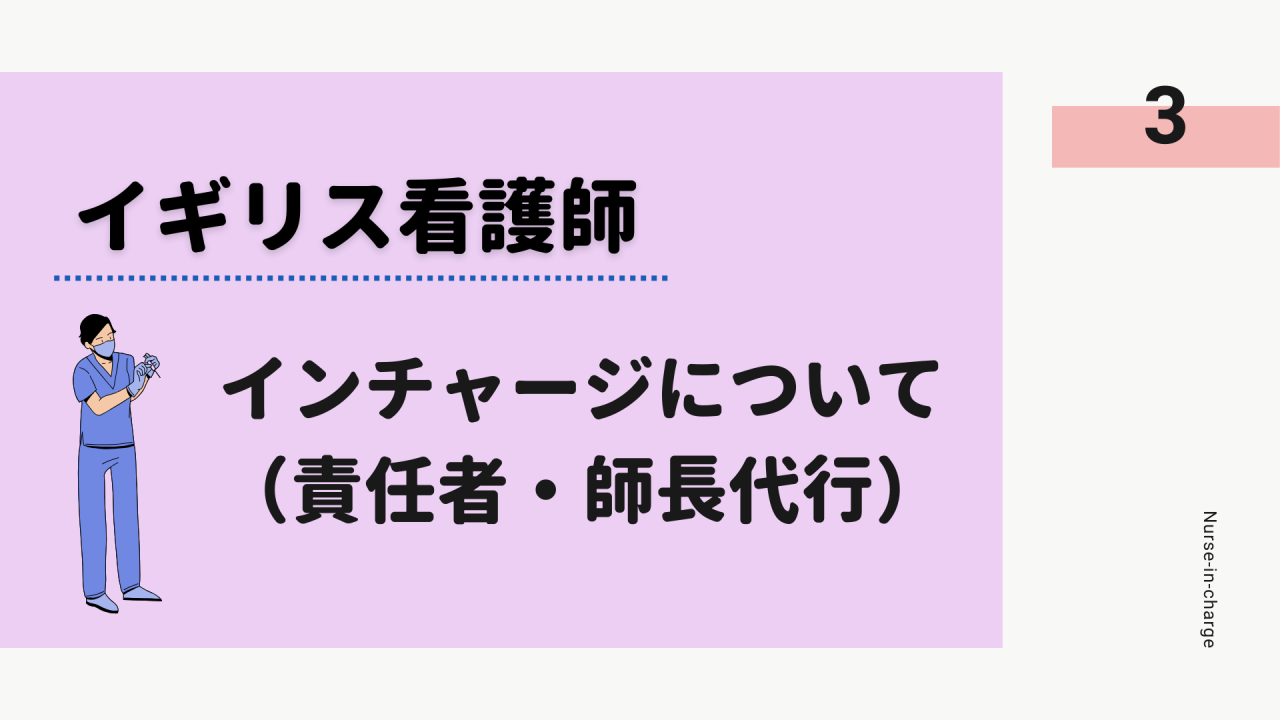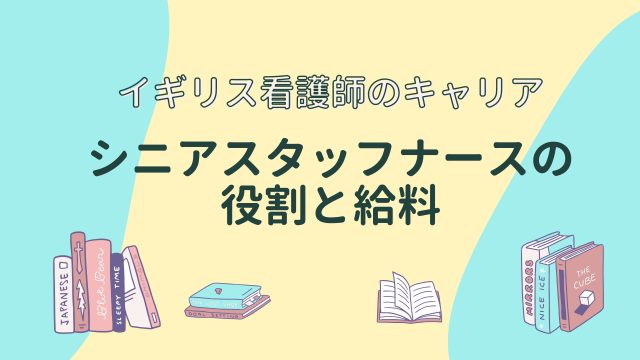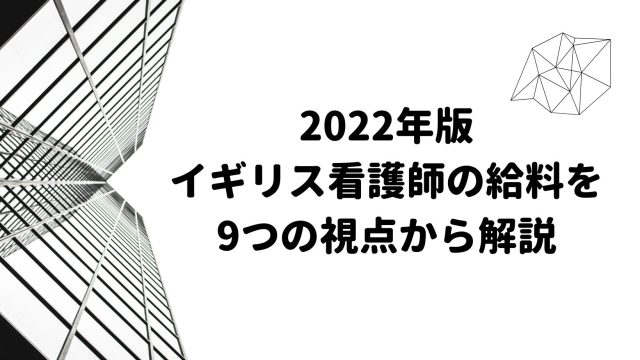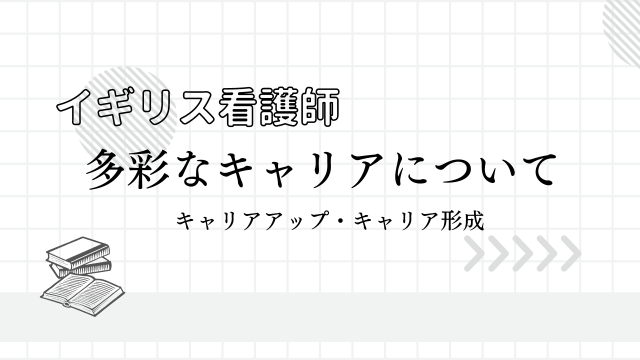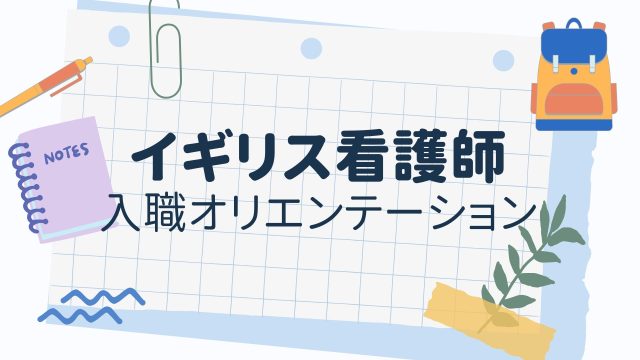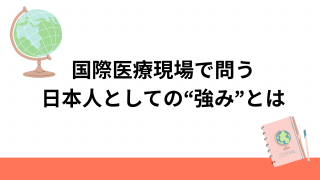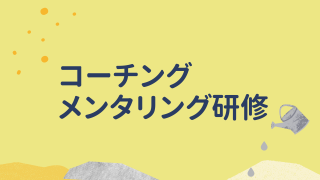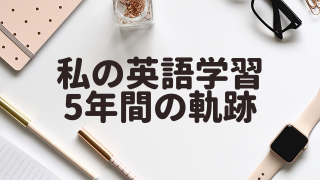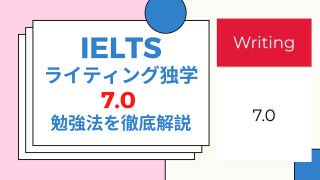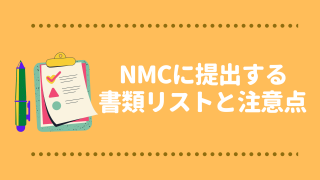イギリス看護師、インチャージの実際(病棟編)
こちらの記事で病棟で働くシニアスタッフナースの役割についてシェアした。
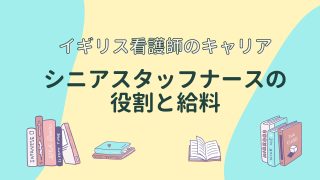
病棟シニアスタッフナースの役割はさまざまあるが、今回は日々の業務の中心となるインチャージについてシェアする。
患者を受け持つ場合の病棟看護師の一日の流れ(日勤・夜勤)については、こちら。
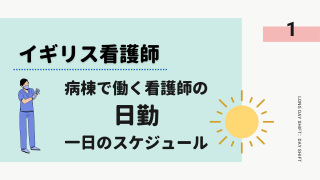
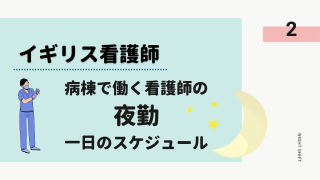
インチャージとは
インチャージ(In-charge)とは、シフト中に病棟やユニットの責任を持つ看護師を指す。日本の病院(病棟)でいうと、勤務帯の責任者といった表現が近い。
インチャージは日々の病棟業務において人のマネジメント、業務調整、医師や他職種との連携、サポート、クレームの一次対応を行う。日本のリーダーと似ているが、師長不在時は代理・代行としての役割を果たすためインチャージのほうが抱える責任が大きいと感じる。
基本的にバンド6副師長またはシニアスタッフ、師長がインチャージを担うが、経験を積んだバンド5が担当することも多い。
インチャージのリアル
インチャージは骨の折れる仕事で、責任が大きく、色々な場面で判断することを求められるので拒否する人も少なくない。基本的には個人の選択として認められるが、上司の方針や人手不足の職場では強制的にまかされることもある。
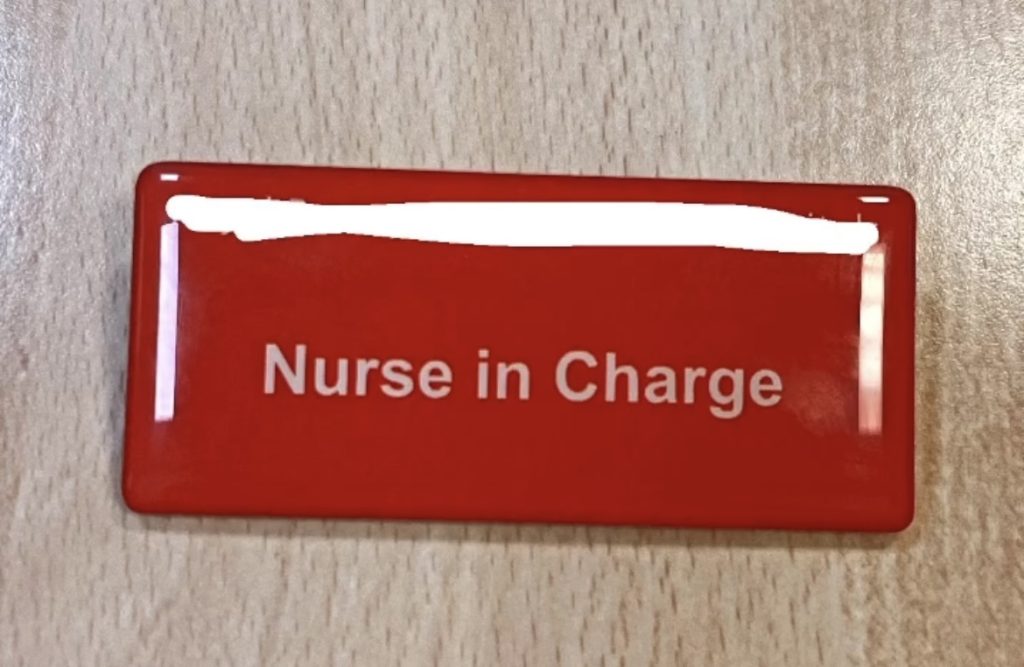 In-Chargeバッジ
In-Chargeバッジ人のマネジメント
スタッフの人員配置、受け持ちをどのように振り分ける。スタッフ一人ひとりのスキルと患者の重症度を考慮して配置を決める。欠員補充のためにスタッフ配置を変更したり、バンクシフトの募集をかけたりする。
日本は勤勉な人が多いため、与えられた仕事はきちんとこなすことが当たり前だけど、イギリスではそうはいかない。仕事への熱意と真面目さは日本と海外で大きな違いがあるので、この文化の違いを考慮しながら働くことが必要になってくる。
スタッフにもよるが、日本では経験しなかったことに遭遇する。
- 勤務中に突然姿を消す
- 指定された時間以上に休憩を取る
- 30分~数時間以上の遅刻
- 担当患者の割り振りに不満を言う
- 緊急入院や転入患者の受け持ちを拒否する
- 勤務中に同僚と口論する
イギリスを含む海外では、不満がある際に我慢せず自己主張をする。悪く表現すれば、言った者勝ちのような風潮があり、チーム内に利己的な人が多いと現場が混乱しやすい。こういった問題が起きたとき、適切に介入するのがインチャージの役割になっている。
人のマネジメントは精神的な消耗が大きく、最も気を遣う部分でもある。各自がプロフェッショナルとして自覚を持って行動すれば、マネジメントにかかる負担は軽減され、他の業務に集中することができる。個性とスキルが多様なスタッフをまとめ、良いチームワークを生み出せるかどうかは、インチャージの力量次第なところがある。

業務調整
イギリスでは、さまざまなことが行き当たりばったりで進むことが多い。事前に計画を立て、その通りに物事を進める日本とは対照的に、イギリスでは計画通りにいかないことが通常運転である。日々の業務調整はまさにミッション・インポッシブルの連続であり、この無茶ぶりのミッションをどうポッシブルに変えていくかが、インチャージに求められるスキルである。
私は循環器に勤めているが、手術室への搬送・検査・治療後の帰室依頼が同時に3件来ることもある。そのような場面では、患者の安全を守りつつ、スタッフに適切な休憩を取らせるバランスも考慮しながら、的確に業務を調整する必要がある。
医師や他職種との連携
日中の場合、医師はチームになって患者の回診を行う。回診後に患者の治療プランが決まるので、そのプラン通りに指示が出されているか確認する。記録と指示が異なるときや指示に質問や疑問があるときは、その都度スタッフを代表して医師に確認する。また、患者の状態変化を報告したり、退院サマリーや処方の手続きなどをフォローアップするのもインチャージの役割になっている。
他職種との連携もかなり重要。イギリスでは、理学療法士、作業療法士、薬剤師、退院支援などの他職種は専門分野に特化して患者をサポートする。日本では看護師が多くの患者情報を把握し支援する傾向があるが、イギリスでは各職種が高い専門性を持って業務を分担している。たとえば、家の間取り、必要な介護用品、訪問介護の手配などは作業療法士がすべてアセスメントし、計画を立てる。それぞれの職種が独立して機能しているため、円滑な連携を図るには、日頃からのコミュニケーションが不可欠である。
サポート
スタッフが困っているときにはサポ―トをする。インチャージの自分自身が手伝うのか、それとも他のスタッフに依頼するのか、優先度と緊急度を考慮して対応を決める。
サポートの匙加減は難しい。インチャージは自分しかいないので、サポートに回りすぎると、インチャージの仕事が進まない。必要以上に手伝うと怠けだすスタッフもいるし、きちんと線引きをすることが大切。
クレームの一次対応
前述した通り、海外では何か不満があったときは自己主張をする文化がある。なかには感情を爆発させる人もいるので、怒鳴られることもある。頻繁にあるわけではないが、数ヶ月に一度は経験するため、日本よりその頻度は高いと感じている。
このようなクレーム対応の矢面に立つのも、インチャージの役割である。激しい怒りをあらわにしたり、涙を流したりする患者やその家族に対し、どのように対応するかによって、事態の収束の仕方が大きく変わる。だからこそ、難しさの中にやりがいもある。
すべてのクレームに対応する必要はなく、インチャージはあくまでも一次対応を担う。自らの判断での解決が困難と考えられる場合には、師長やメイトロン(師長より上位職)に状況を報告し、対応を依頼することが求められる。
インチャージは成長のチャンス
インチャージはストレス度の高い役割だけど、イギリス(およびヨーロッパ)で求められるソフトスキルを飛躍的に向上させる貴重な経験になる。
日本人看護師は海外でも通用し、重宝されるという声を耳にすることがあるが、必ずしも全面的に同意できないところがある。
確かに、海外では日本ほど仕事に対して高い意識を持つ人は多くなく、勤勉な姿勢は一定の評価を得られる。一スタッフとして職場を支える立場であれば、それだけで十分に通用する。しかし、より上のポジションを目指すとなると、それだけでは足りない。バンド6以上のシニアの役職になれば、チーム全体のことを考え、判断し、積極的に行動することを求められる。
イギリスの医療現場では、チーム全体にポジティブな影響を与える人が重宝される。ただ言われたことだけに従って黙々と真面目に働くだけでは、周囲に良い影響を与えることも、チーム内で存在感を示すことも難しい。インチャージを任されたり、さらに上位の役職を目指すためには、リーダーシップや対人関係能力といったソフトスキルを磨くことが不可欠だと思う。
この辺は、日本で生まれ育った人にとってはかなり難しい。日々、試行錯誤しながら現在も学び中。